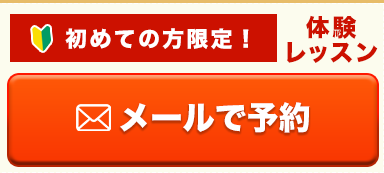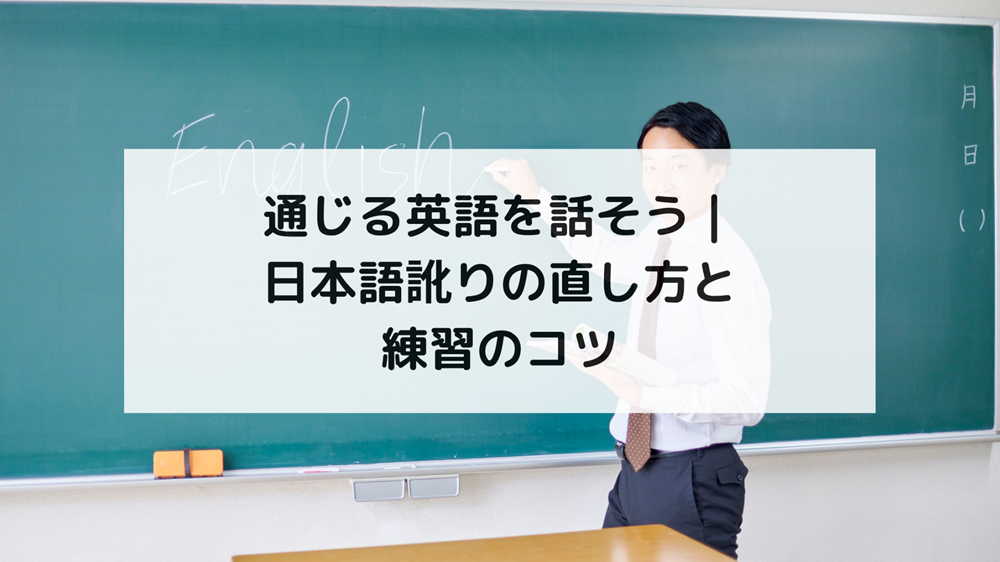
1. 日本語訛りとは?英語発音との違いを知ろう

1.1 日本語訛りとはどういうもの?
英語を話していると、「自分の英語ってなんだか通じづらい…?」と感じたことはありませんか?
それ、もしかすると**「日本語訛り」**が原因かもしれません。
日本語訛りとは、日本語を母語とする人が英語を話すときに、日本語の発音やリズム、イントネーションのクセがそのまま英語に影響してしまう状態のことです。
英語には英語の音の特徴がありますが、日本語の話し方のまま英語を話すと、それが不自然な響きとして伝わってしまいます。
たとえばこんな場面で違和感を感じることがあります。
- 英語で挨拶しても「ん?」と聞き返される
- 単語を一つひとつ丁寧に発音しているのに通じない
- 英語っぽく話しているつもりでも「カタカナ英語」っぽいと言われる
これらの場面では、多くの場合日本語特有の発音パターンが英語に干渉しているんです。
具体的には次のような特徴が見られます。
- 母音を足してしまいがち(「good」が「グッド」となるなど)
- 子音だけで終わる音が不自然になる(「stop」が「ストップ」になる)
- アクセントが平坦で、リズムに強弱がない
これらの要素が合わさることで、「英語のようで英語に聞こえない音」になってしまいます。
ただし、日本語訛りがあること自体は悪いことではありません。
大事なのは、相手に伝わるように通じる発音を身につけることです。
その第一歩が、「なぜ日本語訛りが起こるのか」を理解すること。
1.2 英語と日本語の音の違い
日本語訛りを改善するには、まず**日本語と英語の「音の仕組みの違い」**を知ることが大事です。
この違いを理解しないまま練習しても、なかなか発音は良くなりません。
英語と日本語では、そもそも音の作られ方やリズム感が大きく違います。
ここを押さえておくだけでも、発音の改善スピードがかなり変わってきます。
主な違いはこちらです
- 音の数の違い
日本語は音の数が少なく、子音と母音が必ずセットで発音されます。
一方、英語は子音だけで発音される音や、母音の種類も多く、音のバリエーションが豊富です。 - リズム感の違い
日本語は一つ一つの音を均等に発音する「モーラ(拍)リズム」ですが、英語は「強弱リズム」で、強く読む部分と弱く読む部分がはっきりしています。
この違いが、抑揚のない英語=日本語訛りにつながります。 - 子音と母音の発音方法の違い
日本語では、口の中をあまり動かさずに発音しますが、英語では舌の位置や口の開き方が大きく関係してきます。
特に「舌をどこに置くか」「どれだけ口を開くか」といった動きが大切になります。
これらの音の仕組みを知らずに発音していると、どうしても日本語的な音になってしまうんです。
たとえば、「red(赤)」という単語。
日本語的に「レッド」と発音すると、最後の「d」がはっきり聞こえすぎたり、全体的に平坦なイントネーションになります。
英語らしく聞こえないのは、音の数や強弱の違いによるものです。
こういった違いに気づくことが、日本語訛りを直す第一歩になります。
1.3 なぜ日本語訛りが起こるのか?
多くの日本人が英語を話すと、どうしても「日本語っぽさ」が出てしまいます。
それは、英語力が足りないからではありません。日本語と英語の発音に根本的な違いがあるからです。
理由1:母語の影響が強く残るから
人は最初に覚えた言語の音を基準にして、新しい言語の音を聞き取ろうとします。
そのため、日本語の「音のクセ」が無意識に英語の発音にも表れてしまうんです。
たとえば、日本語は「子音+母音」の音が基本で、単語の語尾に子音だけが来ることはほとんどありません。
そのため、「desk」や「milk」など子音で終わる英単語が、日本語訛りだと「デスク」「ミルク」となってしまいます。
理由2:英語の音を正しく聞き取れていない
発音できない音は、まず聞き取れていないことが多いです。
英語は弱く発音される音や、強く読まれる部分に変化が多く、慣れていないとすべてが平坦に聞こえてしまいます。
そのため、英語のネイティブスピーカーの会話を聞いても、リズムや音のつながりを認識できず、日本語のリズムで再現してしまうのです。
理由3:学校教育で「読む・書く」が中心だった
日本では、英語教育の多くが「文法」「読解」「単語の暗記」中心です。
音の仕組みや口の使い方を教わることは少なく、発音練習も限られていました。
その結果、「カタカナで覚えた音」「ローマ字的な発音」になりやすく、本来の英語の音とズレが生じます。
つまり、日本語訛りは「意識せず自然に身についてしまったクセ」なんです。
このクセは、しっかりポイントを押さえて練習すれば修正できます。
次のセクションでは、日本語訛りの具体的な特徴や失敗パターンを詳しく見ていきましょう。
2. よくある日本語訛りの特徴と原因

2.1 カタカナ英語の影響
英語を話すとき、ついカタカナ表記に頼っていませんか?
実はこの**「カタカナ英語」こそ、日本語訛りの大きな原因**なんです。
カタカナ英語がクセになる理由
日本の学校や日常では、英単語がカタカナで紹介されることがよくあります。
たとえば「computer(コンピューター)」「coffee(コーヒー)」など、あたかも日本語のように馴染んでいる単語も多いですよね。
しかしこのカタカナは、本来の英語の音とはかけ離れていることが多いです。
- 音が増えてしまう(例:stop → ストップ)
- 音が伸びてしまう(例:coffee → コーヒー)
- 平坦なリズムになる(強弱がなくなる)
カタカナで覚えてしまうと、その音が頭に染みついてしまい、英語を話すときも無意識に同じように発音してしまうんです。
よくある失敗パターンとその原因
こんな失敗が多いです。
- 単語の語尾に母音を足してしまう
例:「desk」を「デスク」、「book」を「ブック」と発音する
→ 日本語では子音で終わる音がないため、母音を付け足してしまいます - 語中の強弱がない
例:「computer」をすべて同じ調子で「コンピューター」と読む
→ 英語のリズム感がなくなり、平坦で機械的な印象になります - 単語単位でしか発音できない
例:「I want it」を「アイ・ウォント・イット」と区切る
→ 英語では音がつながるため、これだと不自然になります
カタカナ英語に慣れすぎてしまうと、聞く力も発音も伸びにくくなります。
解決策:カタカナを捨てて「音」で覚える
改善するには、まずカタカナ表記を見ない・使わないこと。
代わりに、ネイティブの音声を聞いて、「実際にどう聞こえるか」で覚えることが大切です。
- ネイティブ音声を何度も聞く
- 音のまま真似する(文字に頼らない)
- 発音するときはリズムと強弱を意識する
頭の中にある「日本語的な音のイメージ」を、英語の音に上書きしていくような感覚です。
これだけでも、カタカナ発音のクセは少しずつ改善できます。
2.2 子音の発音が弱くなる理由
日本語訛りの発音でよく見られる特徴のひとつが、子音の発音が弱くなるという現象です。
単語の始まりや語尾の子音がぼやけてしまい、ネイティブにうまく伝わらないことが多いです。
日本語には「子音だけ」の音が少ない
日本語では、たいてい子音と母音がセットになっています。
たとえば「か」「さ」「た」など、すべて「k+a」「s+a」「t+a」といった形で発音されます。
そのため、英語のように子音だけで発音する音に慣れていないんです。
- 英語:dog →「d」「g」の子音で終わる
- 日本語的な発音:ドッグ → 語尾に「u」や「gu」を足してしまう
これが、英語らしさが薄れてしまう理由のひとつです。
よくある失敗例とその原因
- 語尾の子音を省略または母音化してしまう
例:「cat」→「キャットゥ」または「キャッ」になってしまう
→ 子音を明確に言えず、日本語的な語尾になる - 破裂音が弱すぎて伝わらない
例:「pick」と「pig」の区別がつかない
→ 無声音・有声音の区別ができていないことが多い - 舌や唇の使い方に慣れていない
例:「v」「f」「l」「r」などがすべて「ブ」や「フ」に聞こえてしまう
→ 舌や唇の使い方を変える意識がないと、すべて似た音に聞こえます
これらの問題が重なると、「聞こえない英語」になってしまいます。
解決策:口の動きと舌の位置を意識する
子音を強調するために、以下のようなポイントを意識してみてください。
- 発音前に「どこに舌を置くか」「どの筋肉を使うか」を考える
- 鏡の前で口の動きをチェックする
- ゆっくり発音して、語尾の子音まで丁寧に発音する練習をする
たとえば、「sit」と「sheet」の違いを発音するときは、舌の位置が少し変わるだけでもまったく違う音になります。
そういった細かい動きを意識するだけで、英語らしさは大きくアップします。
子音の精度が上がると、通じる英語にグッと近づきます。
2.3 アクセント・抑揚のずれによる違和感
英語を話しているのに「通じにくい」「機械的に聞こえる」と感じたことはありませんか?
その原因のひとつが、アクセントや抑揚のつけ方が英語とズレていることです。
日本語は「平坦」、英語は「強弱」がある
日本語は基本的に、一つひとつの音を均等な強さで発音します。
一方で英語は、「強く読む音」と「弱く読む音」が交互に現れ、リズムに高低と強弱があるのが特徴です。
たとえば「banana」という単語では、英語では2番目の「na」にアクセントがあります。
ですが、日本語的に読むと「バナナ」とすべて同じ調子になり、英語としての自然な抑揚が失われてしまいます。
よくある失敗パターンと原因
- どの音も均等な強さで発音する
例:「important」を「インポータント」と言ってしまう
→ 強弱がないことで、英語独特のリズムが崩れます - アクセントの位置がずれてしまう
例:「record(名詞)」を動詞のように「リコード」と読んでしまう
→ アクセント位置の違いで意味まで変わってしまうこともあります - イントネーションが上がり下がりしない
→ 質問文でも語尾が上がらず、感情のない話し方に聞こえることがあります
これらが重なると、「単語は合っているのに通じない英語」になってしまいます。
解決策:「英語のリズム」を耳と口で覚える
発音を直すには、単語だけでなくリズム全体で英語をとらえることがポイントです。
- ネイティブ音声を何度も聞いて、強く読まれる部分を意識する
- 自分の声を録音して、抑揚があるかをチェックする
- 単語だけでなく、フレーズ全体をリズムよく真似する
たとえば「Do you want some coffee?」という一文も、英語では「ドゥユワンサムコーフィー?」のように、速く・強弱のあるリズムで発音されます。
これを平坦に「ドゥ・ユー・ウォント・サム・コーヒー」と発音すると、ネイティブには不自然に聞こえてしまいます。
アクセントと抑揚を意識するだけで、英語らしい発音にぐっと近づきます。
3. 英語の音を正しく理解する方法

3.1 舌の位置と口の形を意識しよう
英語らしい発音には、舌の位置と口の形がとても重要です。
日本語はあまり口を動かさずに発音できますが、英語は音に応じた正しい口の使い方が求められます。
特に「LとR」「FとV」など、日本語にない音を出すには、舌や唇の動きを意識する必要があります。
鏡を見ながら練習するだけでも、発音の精度はぐっと上がります。
ポイントまとめ
- 舌の位置を意識(例:Lは舌先を歯の裏に、Rは舌を奥に引く)
- 口の開き方を変えるだけで母音の違いが出せる
- 唇の丸め方をしっかり意識(例:foodの「oo」など)
- 鏡で口元を確認しながら練習するのがおすすめ
3.2 英語特有のリズムと強弱の感覚
英語は「強く読む音」と「弱く読む音」が交互に現れるリズムのある言語です。
一方、日本語は音の強さがほぼ均等なので、英語のような抑揚が苦手になりがちです。
単語ごとに切って発音すると、英語らしさがなくなり通じにくくなります。
自然な英語らしさを出すには「強弱リズム」を意識することが大事です。
ポイントまとめ
- 英語は「強弱リズム」、日本語は「均等リズム」
- 重要な語(動詞・名詞)を強く読む意識を持つ
- 短い文も“歌うように”発音してみるとリズム感がつかみやすい
- 単語ごとではなく「フレーズ単位」で練習すると効果的
3.3 ネイティブの音を「聴き取る力」の鍛え方
発音をよくするには、まず正しい音を聞き取れる耳をつくることが大切です。
英語は「音がつながる」「省略される」など、実際の音と文字の見た目が異なります。
聞き取れない音は真似もできないので、まずはネイティブの話し方に耳を慣らしましょう。
聞こえるようになることで、発音の精度も一気に上がります。
ポイントまとめ
- 音のつながり(リンキング)や省略(リダクション)を意識
- スクリプト付き音声で「音と意味」を一致させて聞く
- 聞いた音を繰り返して真似する(録音→確認が効果的)
- 一語一語ではなく「かたまり」で聞く癖をつける
4. 日本語訛りを直すための具体的な練習法
4.1 カタカナに頼らない練習方法
英単語をカタカナで覚えてしまうと、本来の音とズレた発音になります。
たとえば「coffee」を「コーヒー」と言うと、英語らしさがなくなってしまいます。
正しい音を身につけるには、カタカナ表記を一切使わない練習が効果的です。
カタカナを捨てることで、本物の英語の音が耳と口に定着します。
ポイントまとめ
- カタカナ表記を見ない・書かない
- 音声を聞いて“耳コピ”で覚えるクセをつける
- 意味を理解せず、まずは「音だけ」真似する練習もあり
- 書くより“発音→聞く→真似”の反復が大事
4.2 自分の発音を客観的にチェックする方法
発音練習では「ちゃんと発音してるつもり」が落とし穴です。
自分の声を聞き返してみると、「思ったより日本語っぽい…」と感じることがよくあります。
発音を改善するには、自分の声を客観的に確認することが欠かせません。
録音して聞き返すだけで、発音のクセに気づけるようになります。
ポイントまとめ
- スマホやPCで自分の発音を録音する
- ネイティブの音声と聞き比べて違いを探す
- 客観的に聞くことで、母音・子音の抜けに気づける
- 繰り返すことで改善ポイントが明確になる
4.3 ネイティブ音声の真似方と注意点
ネイティブの話し方を真似する「音まね練習」は、発音改善にとても効果的です。
ただし、やみくもに真似するだけでは効果が薄く、誤った発音を覚えてしまうこともあります。
コツを押さえて真似することで、正しい英語のリズムや音が身につきます。
真似るときは「耳」「口」「録音」の3つをセットで活用しましょう。
ポイントまとめ
- 短いフレーズを選び、リズムごと真似する
- 意味を理解しながら感情も込めて発音する
- 毎回録音して、ネイティブと聞き比べる
- 完璧を目指さず、まずはリズムと抑揚に集中する
4.4 初心者が気をつけるべき練習の落とし穴
発音練習を始めたばかりの頃は、「頑張ってるのに通じない…」と感じやすいものです。
その多くは、練習方法や意識のポイントにズレがあるのが原因です。
効果的な練習にするには、初心者が陥りやすい失敗を避けることが大切です。
遠回りしないためにも、正しい順序と方法で練習しましょう。
よくある落とし穴と対策
- いきなりシャドーイングを始める
→ まずは単語やフレーズで発音を固めてから - カタカナで覚えてしまう
→ 音をそのまま真似して記憶するクセをつける - 長時間詰め込みすぎる
→ 毎日短時間でも“継続”が効果的
5. 発音改善に役立つ学習環境の整え方
5.1 ネイティブ音声を使った実践的なトレーニング
発音改善において、ネイティブの音声は「お手本そのもの」です。
正しい音を体に染み込ませるには、本物の発音を日常的に聞いて真似することがいちばんの近道です。
教材の聞き流しだけでなく、能動的に取り組む姿勢が大切です。
聞いて→真似して→比べて→直す、のサイクルが上達の鍵です。
実践的な練習法の例
- 映画やドラマのセリフを繰り返し音読する
- 短いフレーズ単位で何度もリピート練習
- ネイティブ音声と自分の声を交互に再生して比較
- スクリプト付きの音源で意味と音をセットで覚える
5.2 中級者以上におすすめのシャドーイング活用法
シャドーイングは、英語のリズム・抑揚・スピードを体で覚えるのに最適な方法です。
ただし、初心者には難易度が高いため、中級以上の方におすすめの練習法として取り入れるのが効果的です。
正しい発音をある程度習得したうえで実施すると、音の再現力が一気に伸びます。
耳と口をフル活用することで、英語の“リズム感”が身につきます。
効果的に進めるコツ
- 聞いた直後に“影のように”声を出して追いかける
- 意味を理解したうえで、音だけに集中する時間も確保
- 最初はスピードを落として、慣れたら自然な速さに
- 1日5〜10分の短時間を毎日続けるのがポイント
5.3 一人でも続けられる学習習慣の作り方
発音練習は毎日コツコツ続けることが何より大事です。
でも、忙しい日常の中で継続するのは意外と大変ですよね。
一人でも無理なく続けるには、「習慣化の工夫」がポイントです。
完璧を目指さず“毎日ちょっとだけ”が継続のコツです。
続けるためのアイデア
- 朝の支度中や通勤中にネイティブ音声を聞く
- 寝る前に1フレーズだけ発音練習をする
- 発音チェックを「録音→再生→振り返り」でルーティン化
- 練習記録をつけて、達成感を可視化する
6. まとめ:日本語訛りは直せる!コツコツ継続が鍵
6.1 今日からできる第一歩
日本語訛りの発音は、正しいステップで練習すれば必ず改善できます。
大事なのは「今できること」から始めること。
完璧な発音を目指すのではなく、“伝わる発音”を目標にしましょう。
最初の一歩は小さくてOK。継続が何よりの力になります。
今日からできること
- ネイティブの音声を1日1フレーズだけ聞いて真似する
- 鏡の前で口の動きを確認しながら発音練習
- カタカナ表記を使わず、音だけで覚えてみる
- 自分の発音をスマホで録音し、聞き返してみる
6.2 自信を持って話せる英語を目指そう
発音に自信が持てるようになると、英語を話す楽しさがぐっと広がります。
たとえ少し訛りが残っていても、相手に伝わる発音ができればそれで十分です。
自信を持って話せるようになることが、学習の大きなモチベーションになります。
伝わる体験が「もっと話したい!」につながります。
自信を持つためのヒント
- 完璧を求めすぎず、少しずつ進歩を感じること
- 通じた経験をメモしておくと自信につながる
- 録音を聞いて「前より良くなった」と実感する
- 自分のペースで、楽しんで学び続けることが大切
英語の日本語訛りを直したいなら、Native Soundsへ
通じない原因は、舌の使い方や口の動きのクセかもしれません。
発音の基本から丁寧に学べるつよし先生のレッスンで、自信の持てる英語を身につけましょう。
詳しくは、Native Soundsの公式サイトへ。
https://www.tsuyoshisensei.com/